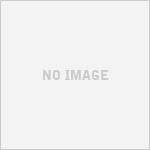お漬物とは

ふだんから日本人にはなじみ深いお漬物ですが、そもそもお漬物の定義とはどんなものでしょうか?またいつぐらいから食べられているのでしょう?
お漬物についてもう少し掘り下げて知ってみると、もっとお漬物が身近に感じられるようになるかもしれません!
お漬物は2種類!保存のきくもの、きかないもの!
まず、漬物はおおまかに分けて2つの傾向に分かれます。
一つは、味噌や塩などに漬け込んだ後、熟成させることで保存性を高めたもの。長期漬けたものは古漬けと呼びます。
もう一つは、生鮮野菜等をお醤油やお酢などの調味料に短時日漬け込んだもので、保存性に乏しいもの、いわゆる浅漬けです。
ちょっと難しいことばも含まれていますが、
厚生労働省の発行している『漬物衛生規範』より、漬物の定義を抜粋して載せておきますね。
通常、副食物として、そのまま摂食される食品であって、野菜、果実、きのこ、海藻等(以下「野菜等」という。)を主原料として、塩、しょう油、みそ、かす(酒かす、みりんかす)、こうじ、酢、ぬか(米ぬか、ふすま等)、からし、もろみ、その他の材料に漬け込んだものをいう。これらは、漬け込み後熟成させ、塩、アルコール、酸等により保存性をもたせたもの(ただし、熟成後調味のための加熱工程のあるものを除く。)と浅漬(一夜漬ともいう。生鮮野菜等(湯通しを経た程度のものを含む。)を食塩、しょう油、アミノ酸液、食酢、酸味料等を主とする調味料、又は、酒粕、ぬか等を主材料とする漬け床で短時日漬け込んだもので、低温管理を必要とするもの。以下同じ。)のように保存性に乏しいものに分類される。(漬物の衛生規範/漬物の定義 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長)
つまり、漬物とは、野菜などを調味料などに、ある一定期間漬け込んだもの。漬け込み具合により、保存性の高いものと低いものはありますが、それらを含めた総称です。
生野菜に塩をかけて食べても、それはサラダであって、漬物ではないってことですね。
塩に漬けると野菜はどうなるの?
では、野菜に塩をまぶして重石をしておくと、野菜の内部はどんな変化が起こっているのでしょう?
とてもよくまとめてある本があったので、引用します。
そもそも植物は無数の細胞からできており、ひとつひとつの細胞は細胞膜に囲まれている。これが食塩などの溶液に触れると、その浸透圧によって細胞膜が破壊され、細胞の中身が外にでてしまったり、逆に外からの成分が入ってくる状態になる。ここに食塩や調味液が入ってきた状態が、「漬かる」ということ。細胞膜破壊が3~4割の場合は浅漬、7割以上でよく漬かった状態になるのだという。(あまった野菜でお漬物/枻出版社)
「塩をまぶし、野菜の水分を抜き日持ちするようにした”保存”の知恵が、そもそもの漬物のはじまりでした」と、宇都宮大学名誉教授 前田安彦先生が語られています。漬物の歴史は、古代中国までさかのぼるそうです。
奈良時代、お漬物は高級品!
日本で確認されている最も古い漬物の記録は、8世紀の天平年間に平城京から発掘された木簡に書かれたものだそうです。そこから奈良時代にかけて、いくつかの漬物記録が見られるそうですが、当時は食塩が貴重品だったため、漬物も高価だったようです。
江戸時代に入ると、『四季漬物塩嘉言』という64品の漬物の漬け方が書かれた書物が発刊されており、この中ではじめて古漬という技法が登場しています。
現在では、お漬物は各地の風土や嗜好にあわせ様々な種類があります。しかし、ここ数十年は減塩、低塩の傾向にあり、調味料の使用量を少なくし、野菜本来の味を生かすことが重視されてきているようです。
以前は、お漬物は高塩分で高血圧の要因と言われた時代もありましたが、野菜の有効な供給源として、近年見直されています。
公開日:
最終更新日:2015/01/16